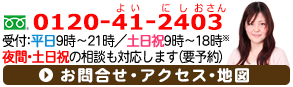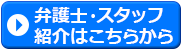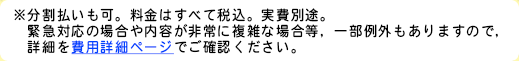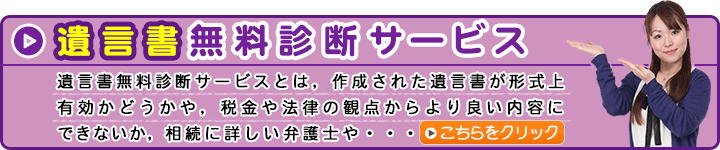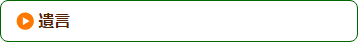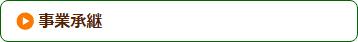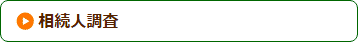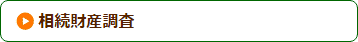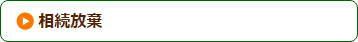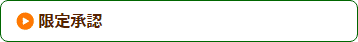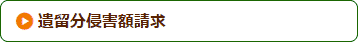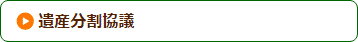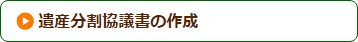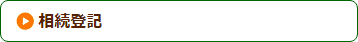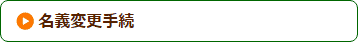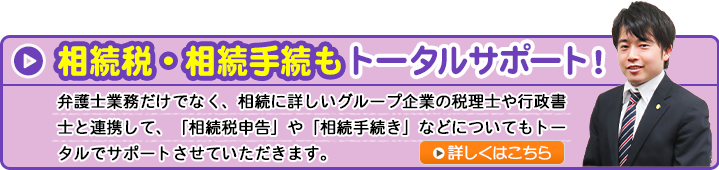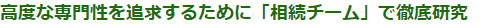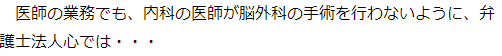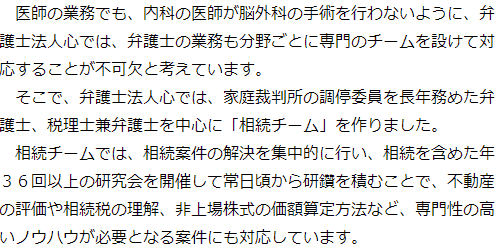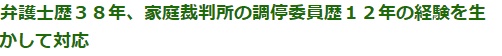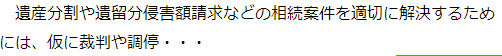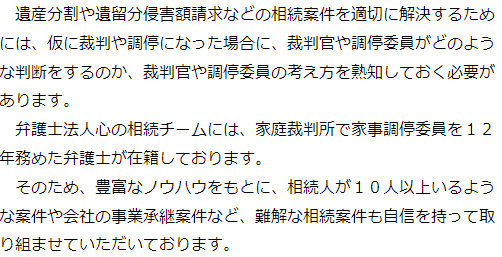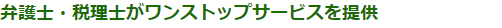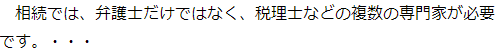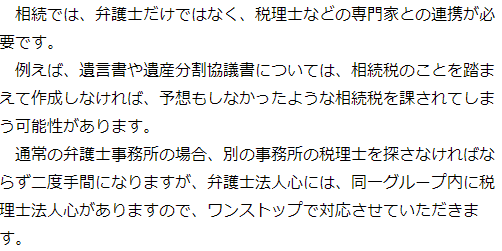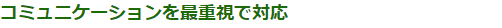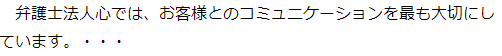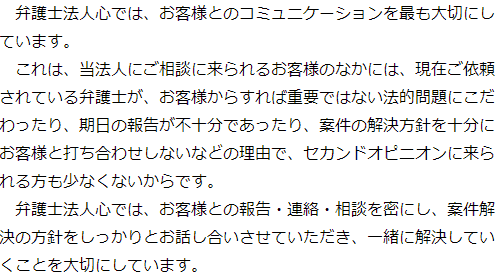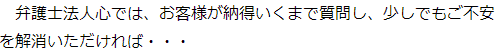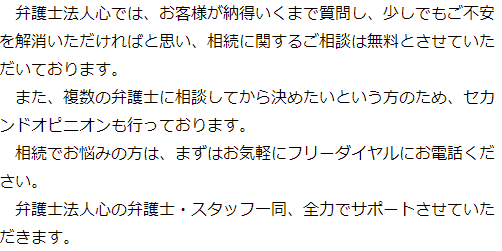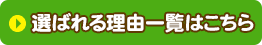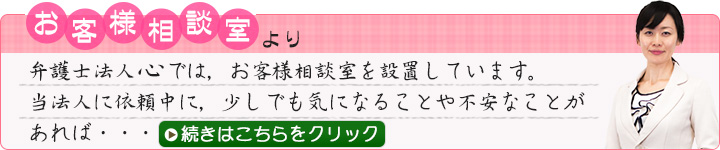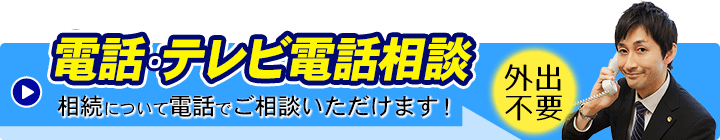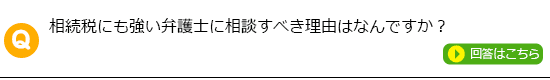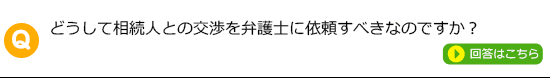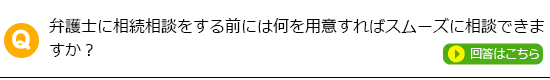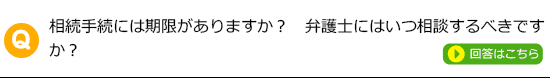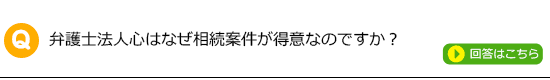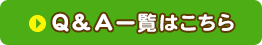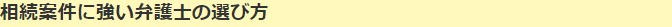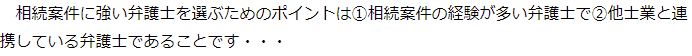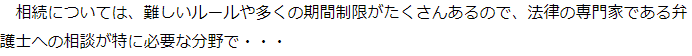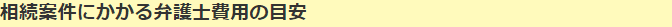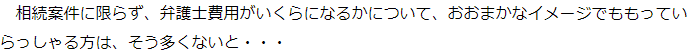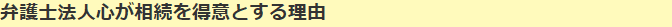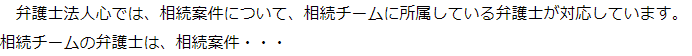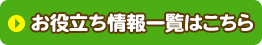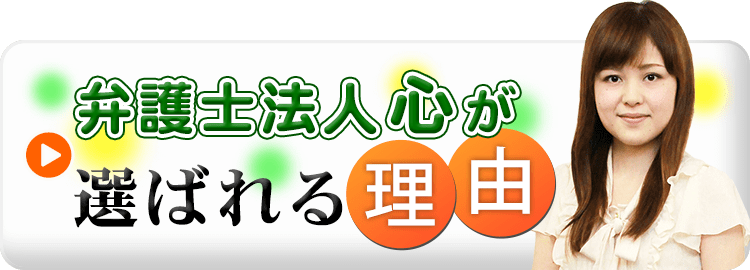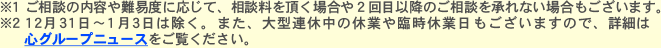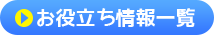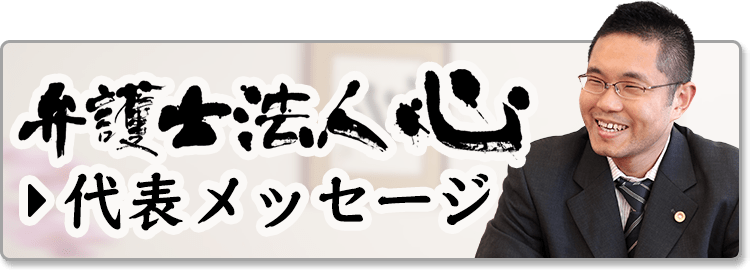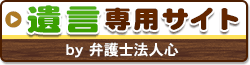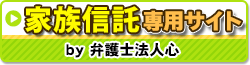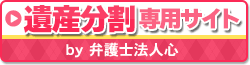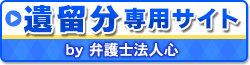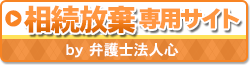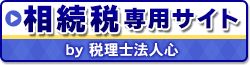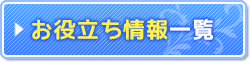ご来所いただきやすい事務所です
当法人の事務所はいずれも駅の近くにあり、多くの方にお越しいただきやすくなっております。所在地の詳細などをご案内しておりますので、ご確認ください。
近鉄四日市駅から弁護士法人心へのアクセスについて
1 南改札口を出ます
近鉄四日市駅で下車されましたら、南改札口を出てください。
改札外にCAFFÉ CIAO PRESSOがあるほうの改札です。


2 階段を降りて西出口を出ます
改札を出てまっすぐ進むと、右手に西出口へつながる階段があります。
そちらを下りて西出口から外へ出てください。


3 正面の建物の3階にお越しください
階段を降りたら、正面のロータリー越しにSTAFF BRIDGEの青い大きな看板と、当法人の「弁護士法人心」という看板が見えます。
当事務所はその建物の3階にあります。

弁護士と各専門家が協力できることの強み
1 各専門家と協力することの必要性

弁護士は、必ずしも他の専門家の分野について、詳しい知識をもっているわけではありません。
相続は、弁護士が取り扱う他の分野と比較しても、他の専門家の分野と密接に関連する部分が多く、弁護士が各専門家と協力する必要性が大きいといえます。
こうした協力が不十分だと、思わぬ不利益が生じかねません。
ここでは、他の専門家との協力が不十分だった例を説明し、弁護士が他の専門家と協力することの重要性を説明したいと思います。
2 他の専門家との協力が不十分だった例
この事例では、多額の相続財産が存在したため、相続税の課税対象になっていました。
ところが、相続人の間における意見対立が激しかったため、申告期限までに相続財産の分割方法についての合意を行うことができませんでした。
そこで、申告期限の段階では、未分割での申告を行い、申告と納付がなされました。
この場合、申告期限の段階では、小規模宅地等の特例を用いることができませんので、3年以内分割見込書を提出し、後日、相続財産の分割方法についての合意が成立した後、小規模宅地等の特例を適用して更正の請求を行い、税金の還付を行う予定となりました。
小規模宅地等の特例を適用できる土地は1つだけであり、その土地を自分が取得する予定であったので、適切に更正の請求の手続を行いさえすれば、税金の還付を受けることができるはずでした。
その後、弁護士が他の相続人との協議を重ね、相続財産の分割方法についての合意が成立する運びとなりました。
予定どおり、小規模宅地等の特例を適用し得る唯一の土地については、自分が取得することとなりました。
その後、合意が成立して半年が経過した後、税理士に更正の請求を依頼しました。
ところが、税理士からは、更正の請求を行うことはできないとの回答がなされました。
税理士によると、更正の請求の期限は、合意が成立してから4か月以内であり、すでに更正の請求の期限が経過してしまっているので、請求を行うことはできないとのことでした。
このような事態は、弁護士と税理士が連携していれば回避できたと考えられます。
例えば、税理士があらかじめ更正の請求の4か月の期限についての情報を弁護士に共有しておくことや、合意成立直後に弁護士から税理士に合意が成立したとの連絡を行うことが想定されます。
こうした事例からも、弁護士と各専門家が協力することがいかに重要か確認できると思います。
3 当法人の体制
弁護士法人心の弁護士や税理士法人心の税理士などが必要に応じて連携し、相続の問題に対処する体制を作っています。
相続の問題でお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
相続を依頼する場合の弁護士の選び方
1 相続について弁護士への依頼をお考えの方へ

ほとんどの方にとって、弁護士に依頼する機会はそれ程多くないと思います。
いざ、弁護士に相続の件を依頼するとなると、どの弁護士に依頼するのが良いのか、よくわからないと迷われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、相続を依頼する弁護士を選ぶ際の判断材料について、まとめたいと思います。
もちろん、以下で記載していることの他にも弁護士との相性などもありますが、弁護士を探す際は、まずは、以下の点を参考にしていただけたらと思います。
2 相続に関する法的問題を網羅的に把握していること
相続に関する法的問題は、多種多様です。
相続は、相続分を計算し、相続財産総額にかけ算すれば良いという、単純な問題ではありません。
例えば、相続財産に不動産が含まれている場合は、不動産の評価を行う必要があります。
その際には、固定資産評価額を用いるのか、相続税申告の際の評価額を用いるのか、査定価格を用いるのか、私的に不動産鑑定士に鑑定評価を依頼するのか等が問題になります。
また、土地上に建物が存在する場合には、現状のままでの評価を行うのか、建物を取り壊す前提での評価を行うのか等も問題になります。
このような問題を網羅的に把握している弁護士であれば、相続財産に土地が含まれていた際に、どのような評価方法が考えられるのか、評価方法の違いによって今後の相続にどのような影響が出るのか等を適切に判断し、より良い相続に向けたアドバイスをしてくれるかと思います。
また、このような情報は書面作成や他の相続人との交渉の場面でも利用できる可能性がありますので、適時利用できるようにするためにも、弁護士が知識を網羅的に把握しておくことが望ましいといえます。
3 調査能力があること
相続の問題では、一番情報を持っているはずの被相続人が亡くなっていますので、残された断片的情報を手がかりに、調査を行う必要があるケースが多いです。
必要となる情報がどこまで得られるかということは、断片的情報に基づく調査が可能であるかどうかによって、大きく異なってきます。
例えば、特定の相続人が、被相続人の相続について、相続時精算課税の申告を行っていたという情報があったとします。
このような情報からは、その特定の相続人が、被相続人からまとまった生前贈与を受けていたことが推定されます。
このような場合は、その特定の相続人に特別受益があり、その相続人の取得財産額を減額調整すべきかどうかについて、検討を行う必要が生じてきます。
このため、例えば、相続税の申告書の記載内容を検証し、贈与された財産の評価額を特定できるかどうかを確認する必要も生じてきます。
このように、相続の問題では、弁護士が、断片的な情報から、どこまで必要な調査を尽くすことができるかどうかが勝負になってくることがあります。
弁護士がこのような調査を尽くせるかどうかは、相続財産を漏らすことなく把握することができるか、交渉上有利になる事情を見つけ出すことができるかどうかにも、影響してきます。
相続で困った場合の相談先
1 相談先を選ぶ際のポイント

相続で困った場合には、どのような弁護士に相談すれば良いのでしょうか。
相談するのが初めての方は特に、相談先選びに迷ってしまうのではないかと思います。
相談先となる弁護士を選ぶ際のポイントとして、「当事者の意向を丁寧に確認できること」「様々な事情を踏まえた納得感のある提案ができること」が挙げられます。
以下で詳しくご説明いたします。
2 当事者の意向を丁寧に確認することができること
相続の当事者は、親族同士であり、無関係の第三者ではありません。
親族間の問題は、損得だけの問題に収まらないことが多く、様々な感情が入り組んだ問題となっていることが多いです。
また、相続に際しては、誰がどの財産を取得するかということだけでなく、今後の先祖代々の祭祀を誰が行うか、引き継いだ財産の管理を今後どのように行うか等、関連する様々な問題が生じてくることも多いです。
このような、様々な感情が入り組み、かつ、関連する問題が多い相続の問題を解決するためには、損得だけでなく、当事者の意向を丁寧に確認する必要があります。
ところが、弁護士は、自分の専門分野との関係で、得か損かということだけしか聞き取らず、限られた問題だけ対応するといった行動に陥りがちです。
先述の相続問題の性質を踏まえると、こうした対応は、当事者にとって、納得感のある解決にはならないことがあります。
例えば、相続人本人が、公平性のある解決を希望しているにもかかわらず、弁護士が、早期解決を強調し、公平感のない解決で合意することを強く勧めるといった行動をとることは、当事者にとって納得感のある解決にはなり難いといえます。
相続では、当事者の意向を丁寧に確認し、納得感のある解決を導き出すことが望まれます。
3 様々な事情を踏まえた納得感のある提案ができること
相続の問題を解決するには、最終的には、弁護士が納得感のある解決を提案する必要があります。
こうした納得感のある提案を行うためには、様々な解決策をシミュレーションし、その中から、最も当事者の意向に沿う解決方法を選び出す力が必要になってきます。
例えば、不動産を売却する方法1つをとっても、特定の相続人が不動産を取得し、その相続人が不動産を売却する相続の方法もあれば、すべての相続人が共同で不動産を売却する相続の方法もあります。
特定の相続人が不動産を取得して売却する相続の方法では、その相続人が今後の不動産の経費、税金等を負担することとなる一方、不動産が高値で売れた場合の利益も得ることとなります。
すべての相続人が共同で不動産を売却する相続の方法では、負担も利益も公平に分担することとなるでしょう。
もっとも、不動産の売却手続が完了し、売却代金を分割するまでに、かなりの時間(場合によっては年単位の時間)を要することもあります。
どちらの相続の方法が適切であるかは、各当事者の希望によって異なってきます。
このように、相続では、様々な解決方法をシミュレーションし、どの解決方法が適切かを選び出す力が必要になってきます。
4 相続で困った場合の相談先の選び方
相続を中心に扱っている弁護士であれば、上記でご説明したようなご提案をすることが可能です。
相談先を選ぶ際には、以上のようなポイントを参考にしていただけましたらと思います。
相続相談を弁護士にするタイミング
1 相続相談のタイミング
相続について弁護士に相談する適切なタイミングは、問題の内容によって様々であるといえます。
ここでは、代表的な例について、相続相談のタイミングを説明したいと思います。
2 相続紛争が発生している場合

相続紛争が発生している場合については、できるだけ早くに相談した方が良いです。
中には、ある程度のところまでは相続人同士で話し合いを行い、相続人同士での話し合いで解決できないことが確定的になった場合に弁護士に相談するという考え方を耳にしたことがある方もいらっしゃるかと思います。
その理由としては、弁護士が介入すると、紛争が激化し、解決までの期間が長期化するからという説明がなされています。
しかし、上記の考え方には、誤解があります。
1つ目は、相続人同士の話し合いの方が、かえって、対立が激化したり、紛争が長期化したりすることがあるというものです。
相続人同士の話し合いについては、相続人全員の合意が成立しない限り、いつまでも続けることができてしまいます。
このため、不合理な理由であっても、たった1人の相続人が反対しているからという理由で、解決に至ることはあり得ないこととなってしまいます。
このような場面では、むしろ、法律論によって整理された主張を行うのが適切です。
法律論によって整理された主張であれば、何らかの法的手続きが取られた場合には、その内容での解決がなされることとなる可能性が高いため、解決に反対し続けることの合理性が低くなるからです。
2つ目は、弁護士に依頼せず、相談して助言を得るに留めることもあり得るということです。
弁護士に相談し、適切な助言を得るだけでも、主張が法的に整理され、相続人間の話し合いが進展することが期待できます。
最初から弁護士に依頼することを考えるのではなく、まずは相談するだけということも可能です。
弁護士に相談し、それでも、相続人間での話し合いでは解決できないと考えるに至った場合には、弁護士に依頼することも検討するとよいかと思います。
このようなことを踏まえると、弁護士に相談する時期を遅らせることには、あまりメリットがあるとは言えません。
やはり、弁護士には、できるだけ早くに相談した方が良いです。
3 相続の手続きが分からない場合
相続の手続きが分からない場合については、必ずしも、いつまでに相談するのが望ましいとは言い難いです。
もっとも、いずれは相談しようと思っていたものの、相談を先送りにしてしまい、実際に相談できたのはかなり時間が経ってからという事態になることは、しばしばあることです。
相談を先送りにすること自体には何のメリットもないと思いますし、相続手続きの中には期限が決まっているものもありますので、思い立ったら早い段階で弁護士に相談するのが良いのではないかと思います。
相続を弁護士に依頼する場合の費用
1 相続を弁護士に依頼する場面

相続を弁護士に依頼する場面は、大きく分けて2つあります。
1つ目は、弁護士に相続の紛争の解決を依頼する場面です。
この場合、弁護士は相続問題について相手方と交渉し、合意による解決や、裁判手続きによる解決を試みることとなります。
2つ目は、弁護士に相続手続きを依頼する場面です。
例えば不動産の登記変更や、預貯金・有価証券等の名義変更手続きを依頼することが考えられます。
弁護士の費用は、上記の2つの場面で大きく異なってきます。
以下では、それぞれの場面について、弁護士に依頼する場合の費用を説明したいと思います。
2 弁護士に紛争の解決を依頼する場面
弁護士に紛争の解決を依頼する場面では、多くの事務所では、着手金と報酬金が発生します。
着手金は事件を依頼した時に発生する費用であり、報酬金は事件が解決した時に発生する費用のことです。
もっとも、事務所によっては、特定の案件については、報酬金のみが発生するものとしていることがあります。
当法人も、相続の案件については基本的に着手金は発生せず、報酬金のみが発生することとしていますので、ご依頼いただきやすいのではないかと思います。
また、多くの場合、着手金については請求金額の何%、報酬金については請求が認められた金額の何%というように定められています。
このように、請求した金額、請求が認められた金額に応じて、費用負担が決まってくることとなります。
もちろん、別の計算方法で費用を算出している事務所もありますので、弁護士と契約を行うにあたっては、どのようにして費用が決まるかをきちんと確認することが大切です必要があるでしょう。
着手金と報酬金以外にも、出廷費(裁判に対応する際の費用)や実費等が発生することも多いです。
このように、依頼する弁護士事務所によって費用の設定が異なりますので、詳細については、弁護士と契約する前際に不明瞭な部分が残らないようにご確認くださいしっかり確認することが大切です。
3 弁護士に相続手続きを依頼する場面
相続手続きについては、一定の手数料が発生することとなります。
手数料の定め方についても、事務所によって異なっています。
例えば、手続きを行う法務局、金融機関、証券会社の個数によって手数料が定まることもあれば、手続きの対象となる財産の額によって手数料が定まることもあります。
このため、同じ案件でも、事務所ごとに費用負担は大きく異なってきます。
やはり、弁護士と契約を行うにあたっては、費用の算定方法について、きちんと確認しておく必要がありまするでしょう。
相続で弁護士に相談すべき場合
1 法律問題についての相談ができるのは原則として弁護士のみ

弁護士は法的問題の専門家です。
法律上、法律問題についての相談ができるのは、原則として弁護士だけであることとなっています。
このため、相続について、すでに法律問題が発生している場合や、将来法律問題が発生する可能性がある場合には、弁護士に相談すべきです。
とはいえ、一言に法律問題といっても、具体的にどのような問題が該当するかについては、イメージしにくいと思います。
そこで、ここでは、生前対策の段階を例として、弁護士に相談するとよい具体的な場合を説明したいと思います。
2 生前対策について弁護士に相談すべき場合
⑴ 推定相続人間の関係が険悪になってしまっている場合
将来相続人となる可能性がある人のことを、推定相続人といいます。
推定相続人間の関係が険悪になってしまっていると、将来、相続が発生した場合に、相続についての話し合いが困難になってしまい、法的紛争が発生するリスクがあります。
このような場合には、遺言を作成し、あらかじめどの財産を誰が取得するかを決めておいたり、生前贈与により、あらかじめ財産移転を済ませておいたりすることにより、相続についての話し合いを行う必要性を低減させ、将来の法的紛争を事前に回避できるようにするとよいです。
弁護士は相続の紛争問題に対応できるため、どのような点が争点になりやすいのかを知っています。
遺言の内容が争いの火種となってしまうことを防ぐためにも、まずは弁護士にご相談ください。
⑵ 推定相続人間で不公平感が生じてしまっている場合
推定相続人間で不公平感が生じてしまっていると、将来、相続が発生した場合に、取得すべき財産割合についての意見対立が生じ、法的紛争が発生するリスクがあります。
具体的には、一部の推定相続人が介護を行っていたり、無償または低額の給与で家業に従事していたりする場合が考えられます。
他にも、一部の推定相続人が多額の生前贈与を受けている場合もこれにあたる場合があります。
表面的には、推定相続人が不公平感を表明していなかったとしても、内心では、不公平感を抱いてしまっていることもあります。
このような場合も、遺言を作成し、推定相続人間で取得できる財産額に差を設けておいたり、生前贈与により、あらかじめ財産を譲渡しておいたりすることにより、不公平感が解消され、将来の法的紛争を事前に回避できる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。
相続の生前対策をお考えの方へ
1 相続の生前対策の目的

相続の生前対策は、様々な目的で行われています。
どのような目的で生前対策を行うかによって、相談すべき専門家も変わってきますので、まずはご自身の中での生前対策の目的をはっきりさせることをおすすめいたします。
ここでは、弁護士に相続の生前対策をするとよい場合について、説明したいと思います。
2 弁護士に相続の生前対策を相談するとよい場合
相続開始後の紛争を予防することが主な目的である場合には、弁護士への相談が有効です。
紛争を予防するための主たる手段として、遺言の作成があります。
もっとも、ただ、遺言を作成しただけでは、紛争を予防できないおそれがあります。
例えば、特定の人にすべての財産を相続させるという遺言を作成しただけでは、他の相続人から遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。
これを予防できる内容にするためには、他の相続人が遺留分相当額の財産を取得するという内容の遺言を作成することが考えられます。
また、作成した遺言については、相続開始後に、内容の実現に向けた行動を行う必要があります。
この内容の実現に向けての行動は、原則として遺言執行者が行います。
この遺言執行者に弁護士を指定しておくと、必要な相続手続き等がスムーズに進むかと思われます。
このように、遺言執行も含めてあらかじめ委託する目的から、遺言を弁護士に相談されるケースもあります。
3 ご相談は弁護士法人心へ
このように、相続開始後の紛争を予防するという目的、相続開始後の遺言内容の実現を信頼できるものに任せるという目的で生前対策を行うのでしたら、弁護士に相談することをおすすめいたします。
弁護士は、法律の専門家として相続の紛争案件を対応しているため、どのような遺言を作成すれば紛争を回避できるのか、遺言内容の実現の際にどのような点に注意をすべきなのかについて、詳しい知識と経験を有していると考えられます。
こうした知識と経験を有しているのは、他の専門家にはない、弁護士ならではのことであるといえます。
当法人にも、相続の案件を集中的に取り扱い、生前対策に関する知識や経験を有した弁護士が在籍しておりますので、相続の生前対策についてのご相談がありましたら、どうぞ当法人までご相談ください。
弁護士に相続を相談してから解決までにかかる時間
1 弁護士が対応する相続問題

弁護士が対応する相続問題には、様々なものがあります。
相続財産の分け方が問題になっている場合には、遺産分割を弁護士に依頼される方がいます。
被相続人が作成したとされる遺言が存在するものの、実際には被相続人ではない人が遺言を書いた場合や、遺言を作成した当日、被相続人が判断能力を喪失していた場合等、遺言の有効性に問題があるケースには、遺言無効確認を弁護士に依頼される方もいます。
遺言の有効性は争わないものの、相続人に最低限保障された権利として、遺留分侵害額請求を弁護士に依頼される方もいます。
このように、弁護士が解決する相続問題は様々ですが、解決方法については、共通点が存在します。
ここでは、それぞれの解決方法について、解決にかかるまでどの程度の時間がかかるのかを説明したいと思います。
2 協議による解決にかかる時間
双方が法的手続きによる解決を希望しない場合や、紛争の長期化を希望しない場合には、協議により意見を調整し、解決に至ることが期待できることがあります。
この場合にかかる時間は、相続人や相続財産の調査から始めなければならない場合には、目安として、調査のため、1か月から2か月の期間を想定しておいた方が良いです。
その後、双方の意見調整のため、目安として、さらに1か月から3か月の期間を想定しておいた方が良いです。
ただし、法的な争点が多い場合、追加で調査が必要な事項がある場合、意見の相違が大きい場合には、さらなる時間を要することもあります。
3 法的手続きによる解決にかかる時間
双方の意見調整が期待できない場合には、法的手続きによる解決を試みることとなります。
法的手続きとしては、家庭裁判所における調停、審判、地方裁判所における訴訟があります。
法的手続きによる解決を行う場合には、双方の意見の調整にとどまることもあれば、法的争点について全面的に審理がなされることもあります。
双方の意見調整にとどまるのであれば、1回から2回の期日、期間にすると2か月から3か月での解決が目安となります。
他方、法的争点について全面的に審理がなされる場合には、半年から、長いと年単位の期間を要することもあります。
相続の無料相談をお考えの方へ
1 無料相談が活用できる場面

無料相談が活用できる場面には、様々なものがあります。
無料相談だから、必ずしも話を聞いただけで解決できるような相談にしか適しないというわけではなく、複雑な紛争に直面している場面でも、無料相談が生きてくることがあります。
ここでは、無料相談を用いるのが有益であると考えられるいくつかの場合について、説明したいと思います。
2 いくつかの法的なアドバイスを受けただけで問題が解決できる場合
無料相談は、時間が限られていることが多いため、複数のことや複雑なことを質問するのは難しいでしょう。
このことから、いくつかの法的なアドバイスを受けただけで問題が解決できる場合に、無料相談を利用することが考えられます。
例えば、相続の一般的な流れが知りたい場合や、手続きを行ったり書類を取得したりすべき機関が分からない場合、遺産分割協議書の記載の仕方等に不安がある場合などは、法的なアドバイスを受けただけで解決できることも多く、無料相談を利用するメリットがあるといえます。
ただ、現実には、詳細に確認すると、例外的な事例であることが判明し、法的なアドバイスを受けただけでは解決できないということもあります。
このように、無料相談だけでは解決ができないことがわかったため、弁護士に本格的に依頼することを考えるべき状況になることもあります。
3 弁護士にどの程度の関与を求めるべきかが分からない場合
相続は、人生で何度も直面する問題ではないことが多いです。
相続の全体像が把握できておらず、見通しが立っていないと、相続を進めていく中でどのような問題が生じ、専門家にどの程度の関与を求めるべきかが分からないことも多いものと思います。
このような場合には、とりあえず、無料相談を利用し、弁護士に問題の所在を整理してもらい、弁護士の関与がどの程度必要かをアドバイスしてもらうことが有益でしょう。
弁護士に無料相談を行った結果、弁護士が関与しなくても解決できることが確認できたのでしたら、無料相談のみで解決することができるでしょうし、弁護士が関与しなければ解決することができないことが確認できたのでしたら、弁護士に本格的な関与を求めるため、依頼を行うこととなるでしょう。
4 依頼する弁護士を探したい場合
弁護士の本格的な関与が必要な問題であることが判明していたとしても、どの弁護士に依頼するかについて、慎重に検討を行うべき場合があると思います。
依頼をする弁護士が、相続の問題に詳しいかどうか、信頼できる人かどうか等を検討すべきこともあるでしょう。
このような場合には、無料相談を利用し、限られた相談時間の中で、どの弁護士に依頼するのが良さそうかを比較することが考えられます。
有料相談ですと、弁護士を比較するためのコストの負担が生じてしまいますが、無料相談でしたら、このような負担を避けつつ、依頼したい弁護士を選ぶことが可能となります。
相続問題について弁護士に相談すべきケース
1 相続人間の意見対立が生じる可能性がある場合

相続では、遺言がない場合は、相続人全員の意見が一致しない限り、相続の手続きを進めることはできません。
相続人全員の意見が異なる場合は、相続人間の意見を調整し、相続人全員の合意を試みるか、調停や審判の手続きを用いることとなります。
このように、相続人間の意見調整が必要な場面では、法律論に基づく調整が必要となってきます。
これを行うことができるのは、法律の専門家である弁護士のみです。
加えて、実際に法的紛争を普段から対応している者でなければ、どのように法律論を用いるべきか、適切な判断を行うことは困難でしょう。
相続案件を多数扱っている弁護士であれば、そのような対応もしっかり行うことができます。
現に意見対立が顕在化している場合だけでなく、将来、意見が対立する可能性がある場合も、弁護士に相談した方が良いでしょう。
交渉の初期段階でどのような主張を行うかによって、その後に展開できる主張が制限されてしまう可能性があるからです。
意見が対立する前に行っていた主張により、意見が対立した後にはできなくなってしまう主張が生じることもありますので、早い段階から、どのような主張を行うのが良いか、弁護士に相談しておいた方が良いでしょう。
相続人間の意見調整ができたときも、合意内容を遺産分割協議書という書面でまとめる必要があります。
このような場面では、法的に疑義のない遺産分割協議書を作成できなければ、後日、新たな紛争が生じてしまう可能性があります。
このような場面でも、普段から法的書面の作成を行っている弁護士にご相談いただいた方が良いでしょう。
2 連絡を取ることができない相続人がいる場合
相続人間の交流が乏しく、連絡をとることができない相続人がいる場合があります。
そもそも、相続人が誰であるかも把握できないこともあります。
このような場合には、相続人が誰であるかについて、戸籍で調査した上で、相続人の住所を住民票で確認する必要があります。
このような調査は、法律上は、個人でも行うことができますが、現実には、プライバシーを理由に戸籍や住民票をスムーズに取得できないということが起こり得ます。
相続人の住所が特定できた後は、相続人の意見を確認し、意見調整を試みる必要があります。
この場合、面識のない人と連絡を取り、交渉を行うこととなりますが、どのように連絡を取るべきか等、悩ましい問題があります。
相続人の調査については、弁護士が行うことができます。
また、相続人との連絡、交渉についても、弁護士が代理として行うことが可能です。
このように、連絡を取ることができない相続人がいる場合も、弁護士にご相談いただいた方が良いと考えられます。
相続税についてお悩みの方へ
1 相続の問題と相続税

弁護士に相続についてご相談いただく場合の多くは、相続財産の分割方法について、相続人同士での協議がまとまらない場合だと思います。
この場合は、様々な法律問題についての検討を行い、妥当な相続財産の分割方法がどのようなものであるかについての協議を重ね、相続人全員の合意のもとに相続財産の分割を行うことが重要になってきます。
このような検討を行うにあたっては、相続税の問題についても、合わせて検討を行った方が望ましいです。
なぜなら、どのように相続財産を分割するかは、相続税申告にも大きな影響を及ぼすからです。
ここでは、相続の問題が相続税にどのような影響を及ぼすかについて、具体例を説明したいと思います。
2 相続税における特例の利用
相続税には、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減という、相続税の額を大きく減額することが可能な特例があります。
小規模宅地等の特例は、被相続人が居住していた不動産や、被相続人が事業のために用いていた不動産については、一定の面積までは、評価額を減額することができるという特例です。
配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した財産については、一定の額までは、相続税を非課税とすることができるという特例です。
そして、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減については、申告期限までに遺産分割協議等により帰属が確定していなければ、当初申告の段階から特例を適用することができません。
相続税の申告期限は、基本的には、被相続人が亡くなってから10か月間です。
このため、被相続人が亡くなってから10か月以内に、相続財産の分割方法について、相続人全員で合意を行うことが出来なければ、当初申告の段階ではこれらの特例を用いることができず、一旦は多額の相続税を納付しなければなりません。
事案によっては、特例を適用することができないために、納付資金の調達に苦慮する事態に陥ることもあります。
このように、特例を用いて相続税申告を行うことが想定される場合には、申告期限までに協議をまとめる必要があるということに注意しなければなりません。
3 相続税申告についてのご相談
相続税が課税される案件については、弁護士法人心の弁護士と税理士法人心の税理士が連携し、相続人間の協議についての方針等を検討しています。
このように、相続税の観点からも適切な検討をすることができますので、相続の件でお困りの点がありましたら、お気軽にご相談ください。
相続のお悩みを弁護士がサポート
当サイトでは、相続に関するお役立ち情報や、相続を弁護士に依頼するにあたってのポイント等をご紹介しています。少しでもお役に立てればうれしく思います。